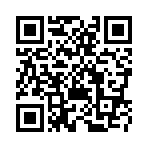昨年のムービーはこちら→医療を救うムービーを見る!
病院の待ち時間も減らせます!医療を救う10の方法はこちら→10の方法を学ぶ!
スタッフへの連絡は こちらより
とりあえず、賛同の気持ちを拍手でクリック

 2009年度ご近所の底力さきがけモデル育成事業 対象企画
2009年度ご近所の底力さきがけモデル育成事業 対象企画
2009年01月02日
大評判!医っQシンポジウム 詳細編その2
医っQシンポジウム
「これからの医療について、今、できること」
の詳細を紹介!
新聞にはこんな感じで取り上げられました↓

まずは、司会&パネリストの紹介
<司会>
・町 亞聖 氏(日本テレビ 報道局記者・厚生労働省担当)
<パネリスト>
・諸岡 信裕 医師(茨城県医師会 副会長, 小川南病院 院長)
・蓮見 孝 教授(筑波大学 人間総合科学研究科芸術専攻)
・石原 望 さん(筑波大学 看護4年生)
・忽那 一平(筑波大学 医学5年生)
シンポジウムの流れ
◆諸岡医師による、現在の茨城の医療の状況説明
・茨城県の医師不足の現状
・後期高齢者医療制度について
↓
◆ディスカッション「これからの医療について、今、できること」
・諸岡医師より医師不足の解決のために何ができるか(専門家の意見)
・その意見に対する蓮見教授のコメント(芸術家・企業人・一般人としての意見)
・各学生のコメント
・医療が向かう方向性、問題点などについてディスカッション
↓
◆質疑・応答
↓
◆パネリストの感想・まとめ
<シンポジウム詳細>わかりやすく、お伝えしますので長文です。
◆諸岡医師による、現在の茨城の医療の状況説明◆
→詳細編その1 参照
http://medicalaction.tsukuba.ch/e19091.html
◆ディスカッション「これからの医療について、今、できること」◆
諸岡医師:
医療者はゆっくりご飯を食べる暇もないぐらい働いているし、さまざまな工夫をしている。
いまこそ、自分たちのためにも国民がしっかり監視し、声を上げることが重要!
看護学生:
助産学実習をしていても、産科医は病院に住んでいるのではないかと思うくらい
、ハードな勤務現場を目にしました。医師の負担軽減のために、産科医と助産師
との役割分化、助産師の知識とスキルの向上が必要だと思います。
医学生:
医療崩壊について改めて、本当におかしな状況であり、なんとかしなくちゃいけないなと思いました。
今回、このようなイベントを開くことができて本当に良かったと思います。
蓮見教授:
こんな状況が何年も放置されている状況が不思議だな~って思う。
みんなで医療を支えていくことが必要。
アート・デザインを医療に持ち込んで、病院という空間を変えていくことが1つできること。
病院は本来、落ち着く場所であり、癒しの空間であり、カラフルな温かみのある空間であるべき。
でも、オフィス系のデザインで覆われているのが現状。
病院がデザイン面で変わることで、そこで働く人たちの癒し空間とへと変わることができる。
たとえば、こんな病院なら医療者も癒される・・・


 より引用
より引用
きちんと整列している物をちょっと傾けてみたり、病院の中に開放感のある空間を作ったり、非制度的な工夫をしていくこと。
日常生活の中には、様々なノイズがあって、実はそれによって癒されている。
病院の中にアートスペースがあったりすることで、医療者にも新しく気づくことがあるだろうし、非医療者にも気付きが生まれる。
病院って「もっと普通の空間なんだ」という認識が生まれると、医療が少しいい方向に向かうのではと思います。
諸岡医師:
病院は安全と機能面を重視して作られています。だからこそ、少人数、高効率で医療ができている。
外国は高い医療費を負担しているから、多くの医療者、充実した設備ができる。
日本はそういう余裕が現在ない状況だから、そういう部分の補完を学生や市民などボランティアの方がやっていければ一番良い形だと思う。
+αの機能まで、医療機関がやろうとすると、今の学校みたいになんでもかんでも求められてしまって、本業がおろそかになる可能性が出てくる。
だから、こうした筑波大学のような総合大学は高い可能性を持っている。医療と他の分野、芸術、体育などの他にない領域も揃っているのだから、本当にみんなでアクションを起こしていきたい。
医学生:
みんなでアクションという点では、環境分野のように芸術家・アーティストが医療分野の現状を訴えるアクションに加わってきていないように感じるのですが、アーティストはどう思っているのでしょうか?
蓮見先生はどう思われますか?
蓮見教授:
医療分野で何かやれるということが頭になかっただけ。筑波大学附属病院で手探りで活動をしている中で感じているのは、病院も変わってきているということ。
何かを実践することで変わっていく、小さな変化が大きくなっていく。小さな波紋もそのうち大きくなるように何かやることが大事。
◆質疑・応答◆
来場者①:
別の政党が政権を取れば、医師不足の問題が解決するということなんですか?根本的な解決になるのでしょうか?
諸岡医師:
今の与党と違う政党を支持することで何か変わるかもしれない。先ほどの話にあったように何かアクションを起こさないとずっとそのままということになってしまう。
来場者②:
自分が取った患者さんを対象とした病院に関するアンケートで、病院内にアート作品の展示などこれまでと違うことをすることに関してどう思うかという項目がありまして、その結果から中にはどうしても受け入れられない・やってほしくないという意見もあるのですが、そのへんを蓮見先生はどうお考えですか?
蓮見教授:
違ったことをやろうとすると、どうしても嫌がる人がいる。でも、「データでとって0%だからやらない」っていうのではいけない。「やめて」と言われたら素直にやめるけど、とりあえずやってみる。という姿勢が大事。論理的に考えないで、核にある感性を大切にしていくこともありなんじゃないかなと思います。
◆パネリストの感想・まとめ◆
諸岡医師:
何かを始めると、必ず紆余曲折するけどそれを経て物事ができあがっていく、これからも心の通った医療ができるようにしていきたい。
蓮見教授:
これからも、学生に支えられ、様々な人に支えられ、アクションが起こしていければなと思います。
看護学生:
まずは、産科医療界の人員として+1になること。そして、私自身が小さな波と
なり、波及していけるような医療人になりたいです。
医学生:
「自分が患者だったら・・」と考えながら行動する医者になりたいと思う。そのためには、今の現状はじぶんが患者だったら絶対嫌だから、まだ学生機関があと1年あるのでなんとかしていきたいと思います。
町氏:
マスコミは医療現場を悪く言い過ぎると言われるが、冷静に取り上げているメディアもある。メディアの人間としてこれからも注意してやっていきたいと思う。このようにアクションを起こし、お互いが気付き、一歩足が出るようなものを提供していきたい。
以上、シンポジウムの詳細でした。
ちゃんと録音などしていなかったため、だましだましのレポートですが、ご勘弁を。悪意はありません。
だれか修正できるかたがいましたら、遠慮なく連絡くださいませ。
参考URL)
茨城県医師会 http://www.ibaraki.med.or.jp/
筑波大学附属病院リニューアルチーム・アスパラバス http://aspalog.exblog.jp/
町氏の取り上げる医療問題ドラッグ・ラグ http://www.dai2ntv.jp/news/druglag/
「これからの医療について、今、できること」
の詳細を紹介!
新聞にはこんな感じで取り上げられました↓

まずは、司会&パネリストの紹介
<司会>
・町 亞聖 氏(日本テレビ 報道局記者・厚生労働省担当)
<パネリスト>
・諸岡 信裕 医師(茨城県医師会 副会長, 小川南病院 院長)
・蓮見 孝 教授(筑波大学 人間総合科学研究科芸術専攻)
・石原 望 さん(筑波大学 看護4年生)
・忽那 一平(筑波大学 医学5年生)
シンポジウムの流れ
◆諸岡医師による、現在の茨城の医療の状況説明
・茨城県の医師不足の現状
・後期高齢者医療制度について
↓
◆ディスカッション「これからの医療について、今、できること」
・諸岡医師より医師不足の解決のために何ができるか(専門家の意見)
・その意見に対する蓮見教授のコメント(芸術家・企業人・一般人としての意見)
・各学生のコメント
・医療が向かう方向性、問題点などについてディスカッション
↓
◆質疑・応答
↓
◆パネリストの感想・まとめ
<シンポジウム詳細>わかりやすく、お伝えしますので長文です。
◆諸岡医師による、現在の茨城の医療の状況説明◆
→詳細編その1 参照
http://medicalaction.tsukuba.ch/e19091.html
◆ディスカッション「これからの医療について、今、できること」◆
諸岡医師:
医療者はゆっくりご飯を食べる暇もないぐらい働いているし、さまざまな工夫をしている。
いまこそ、自分たちのためにも国民がしっかり監視し、声を上げることが重要!
看護学生:
助産学実習をしていても、産科医は病院に住んでいるのではないかと思うくらい
、ハードな勤務現場を目にしました。医師の負担軽減のために、産科医と助産師
との役割分化、助産師の知識とスキルの向上が必要だと思います。
医学生:
医療崩壊について改めて、本当におかしな状況であり、なんとかしなくちゃいけないなと思いました。
今回、このようなイベントを開くことができて本当に良かったと思います。
蓮見教授:
こんな状況が何年も放置されている状況が不思議だな~って思う。
みんなで医療を支えていくことが必要。
アート・デザインを医療に持ち込んで、病院という空間を変えていくことが1つできること。
病院は本来、落ち着く場所であり、癒しの空間であり、カラフルな温かみのある空間であるべき。
でも、オフィス系のデザインで覆われているのが現状。
病院がデザイン面で変わることで、そこで働く人たちの癒し空間とへと変わることができる。
たとえば、こんな病院なら医療者も癒される・・・


 より引用
より引用きちんと整列している物をちょっと傾けてみたり、病院の中に開放感のある空間を作ったり、非制度的な工夫をしていくこと。
日常生活の中には、様々なノイズがあって、実はそれによって癒されている。
病院の中にアートスペースがあったりすることで、医療者にも新しく気づくことがあるだろうし、非医療者にも気付きが生まれる。
病院って「もっと普通の空間なんだ」という認識が生まれると、医療が少しいい方向に向かうのではと思います。
諸岡医師:
病院は安全と機能面を重視して作られています。だからこそ、少人数、高効率で医療ができている。
外国は高い医療費を負担しているから、多くの医療者、充実した設備ができる。
日本はそういう余裕が現在ない状況だから、そういう部分の補完を学生や市民などボランティアの方がやっていければ一番良い形だと思う。
+αの機能まで、医療機関がやろうとすると、今の学校みたいになんでもかんでも求められてしまって、本業がおろそかになる可能性が出てくる。
だから、こうした筑波大学のような総合大学は高い可能性を持っている。医療と他の分野、芸術、体育などの他にない領域も揃っているのだから、本当にみんなでアクションを起こしていきたい。
医学生:
みんなでアクションという点では、環境分野のように芸術家・アーティストが医療分野の現状を訴えるアクションに加わってきていないように感じるのですが、アーティストはどう思っているのでしょうか?
蓮見先生はどう思われますか?
蓮見教授:
医療分野で何かやれるということが頭になかっただけ。筑波大学附属病院で手探りで活動をしている中で感じているのは、病院も変わってきているということ。
何かを実践することで変わっていく、小さな変化が大きくなっていく。小さな波紋もそのうち大きくなるように何かやることが大事。
◆質疑・応答◆
来場者①:
別の政党が政権を取れば、医師不足の問題が解決するということなんですか?根本的な解決になるのでしょうか?
諸岡医師:
今の与党と違う政党を支持することで何か変わるかもしれない。先ほどの話にあったように何かアクションを起こさないとずっとそのままということになってしまう。
来場者②:
自分が取った患者さんを対象とした病院に関するアンケートで、病院内にアート作品の展示などこれまでと違うことをすることに関してどう思うかという項目がありまして、その結果から中にはどうしても受け入れられない・やってほしくないという意見もあるのですが、そのへんを蓮見先生はどうお考えですか?
蓮見教授:
違ったことをやろうとすると、どうしても嫌がる人がいる。でも、「データでとって0%だからやらない」っていうのではいけない。「やめて」と言われたら素直にやめるけど、とりあえずやってみる。という姿勢が大事。論理的に考えないで、核にある感性を大切にしていくこともありなんじゃないかなと思います。
◆パネリストの感想・まとめ◆
諸岡医師:
何かを始めると、必ず紆余曲折するけどそれを経て物事ができあがっていく、これからも心の通った医療ができるようにしていきたい。
蓮見教授:
これからも、学生に支えられ、様々な人に支えられ、アクションが起こしていければなと思います。
看護学生:
まずは、産科医療界の人員として+1になること。そして、私自身が小さな波と
なり、波及していけるような医療人になりたいです。
医学生:
「自分が患者だったら・・」と考えながら行動する医者になりたいと思う。そのためには、今の現状はじぶんが患者だったら絶対嫌だから、まだ学生機関があと1年あるのでなんとかしていきたいと思います。
町氏:
マスコミは医療現場を悪く言い過ぎると言われるが、冷静に取り上げているメディアもある。メディアの人間としてこれからも注意してやっていきたいと思う。このようにアクションを起こし、お互いが気付き、一歩足が出るようなものを提供していきたい。
以上、シンポジウムの詳細でした。
ちゃんと録音などしていなかったため、だましだましのレポートですが、ご勘弁を。悪意はありません。
だれか修正できるかたがいましたら、遠慮なく連絡くださいませ。
参考URL)
茨城県医師会 http://www.ibaraki.med.or.jp/
筑波大学附属病院リニューアルチーム・アスパラバス http://aspalog.exblog.jp/
町氏の取り上げる医療問題ドラッグ・ラグ http://www.dai2ntv.jp/news/druglag/
Posted by medical-q at 09:30│Comments(0)
│シンポジウムの内容