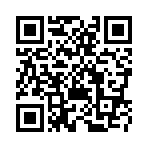昨年のムービーはこちら→医療を救うムービーを見る!
病院の待ち時間も減らせます!医療を救う10の方法はこちら→10の方法を学ぶ!
スタッフへの連絡は こちらより
とりあえず、賛同の気持ちを拍手でクリック

 2009年度ご近所の底力さきがけモデル育成事業 対象企画
2009年度ご近所の底力さきがけモデル育成事業 対象企画
2008年12月29日
日本の医療を救う10の方法!その5
日本の医療を救う10の方法!と題して、1つずつ方法とその効果を紹介していきます。
3日に1回のペースで、約1か月のシリーズにしたいと思います。
どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。
なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。
では、ついに折り返し地点、第5の方法は・・・・
5.大事な説明は家族といっしょに!
まずは、これを確認。
↓
IC=インフォームド‐コンセント【informed consent】(以下IC)
手術などに際して、医師が病状や治療方針を分かりやすく説明し、患者の同意を得ること。解諾(げだく)。
大辞林より ICについて詳しくは→ココ
現場では、「アイシー」と呼ばれるこの
は、実は医療者にとって
けっこうな負担となっています。
というのも、最先端の医療行為を何も知らない人たちに、1から10までわかりやすく説明し理解してもらい、
治療方法を選択してもらう必要があるからです。
説明する内容にもよりますが、短くて15分長いと1時間は説明するようになっています。
しかも、大学病院では大抵その説明に2名の医者が同席します。
(時に医学生も同席させてもらい、勉強させてもらってます。<(_ _)>)
ICの概念が発生し、義務付けられたのは今から約11年前の1997年の医療法改正から。
それまでは患者は医療者から治療方針について説明を一通りされるものの、理解できるほど丁寧に説明されていなかったと思います。
それが今は、医療訴訟のリスクを低減させるべく、手術前には必ずICを行い、医療行為に対する十分な理解を得て紙にハンコを押してもらうというステップを必ず踏むようになっています。
ICの概念の定着→現在の医療者の仕事増加→医療崩壊という構図もあったりします。
(かといって、ICをしないのがいいというわけでは決してありませんので、誤解のないように)
最近はインターネットで最新の論文まで読むことができるので、かなり詳しい人もいますが、実はこれがまた医療者を困らしていたり・・・。
というのも、へたをすると一般の人の方がその病気の治療法について(あくまである特定の病気についてのみですが)医療者より詳しくなっているということがあって・・・。とまぁ、これは長くなるので今回はこの程度にしておきます。
「一般の人にもできること」という本題に戻りますと、
そのICには家族にも来てもらう必要があります。
というのも、手術中など(本人が意識がない状態)に何か緊急事態が発生した場合に、判断をするのは家族などの身内の人になります。
その人たちがICを受けていない場合は、医療者が医療者の価値観で対応することになります。その対応が成功すれば問題はないですが、その対応が悪い結果を招いた際には、当然家族の怒りが発生し、訴訟のリスクとなります。
ということで、ICには手術当日に手術室の隣で待機することができる家族・身内の人が同席することが必須条件となっています。
そして、そのためには必ず
患者さん、その家族、医師の3人以上の都合が合う日程にICを行うことになります。そのため、スケジュール調整がけっこう難しいのが現状です。
私が診察室の中で少なからず複数回見た光景が、
ICに家族が来れなかったから一人で来ました
という光景。
結局、その場合、じゃあまた別の日にICをしましょう。ということになり、最悪の場合は手術日が延期になることすらあります。
せっかく長いこと待たされて、診察室に入ってきたのに、スケジュールを再調整してお帰りいただくということが起こります。
ので、もし予定していたICの日程に家族が来れなくなったら、電話でいつごろなら来れるかどうかを病院に電話してください。
医療者も人なので・・・。
せっかく時間空けておいたのに家族が来てなくてICができないと、非常に落胆してしまいます。
ですので、みなさん病院に来るのは1日がかりになってしまうのはわかりますが、ICの時は家族といっしょに確実に来院するという気持ちが医療を救う1歩となります!
さいごに繰り返します。
5.大事な説明は家族といっしょに!
が医療を救う第5の方法でした。
次はまた3日後、ん、年越しですね。
続いては「tobacco」に関してです。
どうぞお楽しみに。
2009年1月1日(木)頃に次回更新予定です。
どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。
↓医っQのPRのために作ったパンフレットです。ここで紹介している10の方法がまとめてチェックシートになっています。どうぞダウンロードしてお友達にお渡しください。

3日に1回のペースで、約1か月のシリーズにしたいと思います。
どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。
なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。
では、ついに折り返し地点、第5の方法は・・・・
5.大事な説明は家族といっしょに!
まずは、これを確認。
↓
IC=インフォームド‐コンセント【informed consent】(以下IC)
手術などに際して、医師が病状や治療方針を分かりやすく説明し、患者の同意を得ること。解諾(げだく)。
大辞林より ICについて詳しくは→ココ
現場では、「アイシー」と呼ばれるこの
仕事
は、実は医療者にとって
けっこうな負担となっています。
というのも、最先端の医療行為を何も知らない人たちに、1から10までわかりやすく説明し理解してもらい、
治療方法を選択してもらう必要があるからです。
説明する内容にもよりますが、短くて15分長いと1時間は説明するようになっています。
しかも、大学病院では大抵その説明に2名の医者が同席します。
(時に医学生も同席させてもらい、勉強させてもらってます。<(_ _)>)
ICの概念が発生し、義務付けられたのは今から約11年前の1997年の医療法改正から。
それまでは患者は医療者から治療方針について説明を一通りされるものの、理解できるほど丁寧に説明されていなかったと思います。
それが今は、医療訴訟のリスクを低減させるべく、手術前には必ずICを行い、医療行為に対する十分な理解を得て紙にハンコを押してもらうというステップを必ず踏むようになっています。
ICの概念の定着→現在の医療者の仕事増加→医療崩壊という構図もあったりします。
(かといって、ICをしないのがいいというわけでは決してありませんので、誤解のないように)
最近はインターネットで最新の論文まで読むことができるので、かなり詳しい人もいますが、実はこれがまた医療者を困らしていたり・・・。
というのも、へたをすると一般の人の方がその病気の治療法について(あくまである特定の病気についてのみですが)医療者より詳しくなっているということがあって・・・。とまぁ、これは長くなるので今回はこの程度にしておきます。
「一般の人にもできること」という本題に戻りますと、
そのICには家族にも来てもらう必要があります。
というのも、手術中など(本人が意識がない状態)に何か緊急事態が発生した場合に、判断をするのは家族などの身内の人になります。
その人たちがICを受けていない場合は、医療者が医療者の価値観で対応することになります。その対応が成功すれば問題はないですが、その対応が悪い結果を招いた際には、当然家族の怒りが発生し、訴訟のリスクとなります。
ということで、ICには手術当日に手術室の隣で待機することができる家族・身内の人が同席することが必須条件となっています。
そして、そのためには必ず
患者さん、その家族、医師の3人以上の都合が合う日程にICを行うことになります。そのため、スケジュール調整がけっこう難しいのが現状です。
私が診察室の中で少なからず複数回見た光景が、
ICに家族が来れなかったから一人で来ました
という光景。
結局、その場合、じゃあまた別の日にICをしましょう。ということになり、最悪の場合は手術日が延期になることすらあります。
せっかく長いこと待たされて、診察室に入ってきたのに、スケジュールを再調整してお帰りいただくということが起こります。
ので、もし予定していたICの日程に家族が来れなくなったら、電話でいつごろなら来れるかどうかを病院に電話してください。
医療者も人なので・・・。
せっかく時間空けておいたのに家族が来てなくてICができないと、非常に落胆してしまいます。
ですので、みなさん病院に来るのは1日がかりになってしまうのはわかりますが、ICの時は家族といっしょに確実に来院するという気持ちが医療を救う1歩となります!
さいごに繰り返します。
5.大事な説明は家族といっしょに!
が医療を救う第5の方法でした。
次はまた3日後、ん、年越しですね。
続いては「tobacco」に関してです。
どうぞお楽しみに。
2009年1月1日(木)頃に次回更新予定です。
どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。
↓医っQのPRのために作ったパンフレットです。ここで紹介している10の方法がまとめてチェックシートになっています。どうぞダウンロードしてお友達にお渡しください。

糸井重里さんと医療のコラボ
日本の医療を救う10の方法!その10
日本の医療を救う10の方法!その9
日本の医療を救う10の方法!その8
日本の医療を救う10の方法!その7
日本の医療を救う10の方法!その6
日本の医療を救う10の方法!その10
日本の医療を救う10の方法!その9
日本の医療を救う10の方法!その8
日本の医療を救う10の方法!その7
日本の医療を救う10の方法!その6
Posted by medical-q at 10:11│Comments(0)
│日本の医療を救う10の方法